トランスナショナル座談会

自分と異なる文化や意見を
受け入れながら、
みんなで話し合って
開発を進める。
それがSMKのものづくり。
1970年代には海外へ進出、また、早くから外国籍の役員が就任するなど「トランスナショナル※」経営を推進しているSMK。
設計などものづくりの現場でも、さまざまな国の社員が協力し合い、海外事業所などとも頻繁にやり取りしながら開発を進めています。そんなトランスナショナルな開発環境について、ミャンマー、インドネシア、日本の社員から話を聞きました。
トランスナショナル:SMKの概念としては「グローバル+ボーダレス」の意味
MEMBER
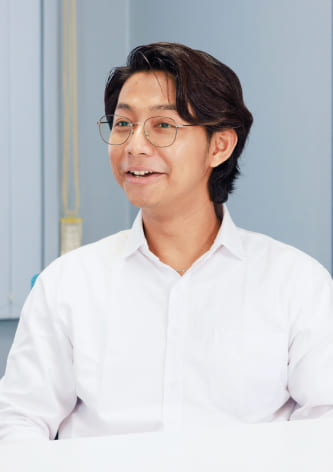
Y.A.
ミャンマー出身
機械学部
海洋機械学科卒
2023年新卒入社
CS事業部車載設計部
東京設計課所属
車載向けUSB Type-Cコネクタの設計を担当。
現在のグループは6人で、内外国籍は1人だが、CS事業部設計部全体ではインドネシアや中国の人も在籍している。海外事業所とは、生産部門のある中国と、自分が設計したものを製造してもらうためにやりとりすることが多い。

W.K.
インドネシア出身
機械学部
機械設計工学科卒
2023年新卒入社
CS事業部車載設計部
東京設計課所属
車載向け同軸コネクタの設計を担当。グループは12名で外国籍は1人。海外事業所とは、主に中国の生産部門、中国、台湾の営業部門とやりとりしている。

K.N.
日本出身
高等専門学校
機械工学科卒
2023年中途入社
CS事業部車載設計部
東京設計課所属
前職のX線測定機器メーカーで測定機器の出荷前検査やメンテナンスを担当した後、転職。現在、車載カメラリアケース部分のコネクタ設計を担当。グループは5人で、全員が日本人。

K.H.
ミャンマー出身
機械学部
海洋機械学科卒
2023年新卒入社
CS事業部Advanced
DX&EX設計部
東京設計課所属
民生品から産機部品まで多様な製品を設計している部署で、micro-USBやe-bike(電動自転車)に使うコネクタの評価試験を担当。20人弱のメンバーのうち、日本人の他には、中国、ミャンマー出身のメンバーが3人在籍。

K.K.
日本出身
工学研究科
応用物理学専攻
大学院修士課程修了
2002年新卒入社
CS事業部Advanced
DX&EX設計部
東京設計課所属 主任
K.H.とは同部・同グループ。e-bikeや太陽光パネル用USBコネクタ、HDMIなどのインターフェースの設計のほか、主任としてグループをまとめ、後進の育成にも取り組む。
CHAPTER 01
ビジョンに共感。
設計に挑戦したい。
ものづくりの会社だから。

みなさんの入社動機を教えてください。

W.K.
もともと物理学が好きで、大学では物理学を使ったものづくりがしたいと機械工学を専攻しました。就職活動の軸も、物理学に近く、学んだ機械工学の知識が活かせることでした。日本はものづくり技術が進んでいるイメージがあったので、インドネシアに加えて日本の会社も探しました。SMKを選んだのは、グローバルな環境で仕事ができると思ったからです。
コネクタに関しては、さまざまな製品に使われるので、幅広い市場や技術に関わることができると思いました。また、電子機器の小型化が進む中、それに対応するためにコネクタを通じてチャレンジができそうだと思い、入社を決めました。

Y.A.
子どものころから設計の仕事をやりたいと思っていました。自分が設計した製品を世界中の人が使うのを見たい気持ちがあったからです。
日本企業を就職先に選んだのは、私の父が相撲好きで、子どものころから日本に親しみがあったことが大きかったですね。SMKを選んだ理由のひとつは、ホームページで「CREATIVE CONNECTIVITY-Challenge, Creativity, Solutions」というビジョンを見たことです。新しい価値を創造していく姿勢に共感を覚えました。

K.H.
大学卒業後は、機械や設計に関わる仕事がしたいと考えていました。日本企業を就職先に考えた1番の理由は、大学の先輩方がたくさん日本にいたからです。2番目は、日本が他の国と比べて発展していて、いろいろな技術を学べると思ったからです。
SMKは、身の回りの電子機器に使われる電子部品を扱っているところが魅力でした。部品という小さなものでも、自分が設計したものを世に出すことがしたいとSMKを選びました。

K.N.
前職はサービスエンジニアでした。機械いじりが好きで約2年間勤務していましたが、毎週どこかに出張するという勤務形態が合わなくて、退職を考えるようになりました。高専出身でロボットなどものづくりが好きだったので、転職活動をするにあたっては設計に挑戦したいと思いました。
ただ、学生時代に勉強していたとはいえ、設計経験ゼロでは受け入れてくれる企業も限られます。そんな中、「コネクタ設計経験がなくてもいい」と言ってくれたSMKに入社を決めました。
ちなみに、コネクタに関して、入社前はもっと電気電子的な要素が強いと思っていました。私はもともと専門が機械工学だったので、うまくキャッチアップできるかなと少し不安だったのですが、入社して機械工学の要素も重要であることが分かりました。加工方法や材料選定、あるいは図面を描くにも、機械工学の知識が有効でした。

K.K.
私は、ものづくりをやっている会社というのが就職先に対する第1条件でした。就職活動をしたころはIT企業に勢いがあった時期で、同級生もたくさん就職していますが、私は実際のものをつくることに興味があったんです。
就職活動をしていく中で、電子部品を扱っている会社に興味が湧き、何社か内定をいただけた中で、最初に内定をいただいたSMKにご縁を感じて入社しました。
CHAPTER 02
笑い声が絶えない職場。
外国籍の社員も日本語が
上手な人が多い。

どんな環境で、どんなコミュニケーションをしながら仕事を進めていますか?

Y.A.
入社前は、ちょっと厳しい雰囲気なのかなと思っていました。男性が多く、あまり話すこともなく、自分の仕事をするだけ、というようなイメージを持っていました。でも、実際はそうではありませんでした。笑い声が絶えない明るい職場です。

K.H.
職場に女性が少なかったので、相談とかもしづらいかなと最初は少し緊張していました。でも、メンターの方もいるし、面談制度などもあるのでいろいろなことを相談できます。だから、職場の雰囲気で、特に気になることはないですね。

K.K.
これまで、アメリカや台湾の方と一緒に仕事をしてきました。今、一緒に仕事をしているK.H.さんも含めて、ここにいるみなさんは日本語が上手ですが、中にはあまり日本語を話せない方もいました。その時は片言の英語や筆談でコミュニケーションしていました。

K.N.
みなさん日本語で話しかけてくれて、すごくありがたいのですが、自分としては、もっと英語ができるようになりたいと思っています。
SMKの設計は、日本で自分がつくったものに関して英語で資料をつくり、理論や構造を海外の会社に説明することがあります。今は、現地の日本人の営業の方に翻訳してもらっていますが、できれば自分で説明できるようになりたい。それは仕事をしていて強く思います。
CHAPTER 03
語学や技術を学ぶ機会から、
キャリアについて考える
研修まで。

仕事をするにあたっての会社からのサポートは?

K.N.
英語の他に中国語などの講習のほか、昇格試験でも語学スコアが必要となっています。だから、自然と勉強する機会はあると思います。

K.K.
通信教育のプログラムが、人事から奨励されています。自分が興味あることは、語学でも技術分野でも受講できますし、受講費用を一部会社が負担してくれます。
勤務しながら語学学校に通学ができるサポート体制もありますよね?入社してから2ヶ月間、午前中だけ仕事をして実践で日本語を学びつつ、午後から語学学校に通うことができるというものです。

W.K.
はい。外国籍の私にとってはとても有益でしたね。
他には——これは国籍に関係なくですが——、部署に入ったときからいろいろな教育を受けることができました。技術についても、簡単な内容からだんだん詳しい内容になる流れだったので、すごく助かりました。
また、私はムスリムで、勤務時間中も5回ほどお祈りをしなければならないのですが、会社がその場所を用意してくれました。本当に感謝しています。

K.H.
私は最近、若手社員研修を受けました。今後仕事にどう向き合い、どのように会社で活躍していくべきかなどについて話し合うものです。これまで自分がやってきたやり方を振り返るチャンスなどもいただけて、とても有意義でした。

Y.A.
私もあの研修はいいと思いました。これまで偶然に起きたことをチャンスと捉えることを学び、またこれからのキャリアについて考えることができました。現在だけではなく、将来にわたってサポートしてもらえると感じました。
CHAPTER 04
「国や地域、文化の違う人にも
伝わりやすく」
を心掛けるように。

ものづくりをするうえで、「トランスナショナルな環境ならでは」と感じることは?

K.K.
無意識のうちに、その国、地域の文化に合わせて、仕事の進め方や注意する点などを変えている気がします。
例えば、日本人だと「何となく察して」みたいなコミュニケーションでいいけれど、海外の人には伝わりません。だから、言葉に気を付けたり、伝えるための準備をしたりしています。

K.N.
それはありますね。試作品をつくるときなど、日本の製造会社は注意すべき点や加工で大変なところを自分たちで判断して、図面に記載された情報以上のことをやってくれたりします。でも、海外の会社は、そうではないこともあります。設計の意図と異なるものが出来上がってしまう場合もありました。
けれど、それは伝える側の人間が変える方が良いのかなと思っています。だから、文化が異なる人や全く知識がない人が見てもわかるもの、言葉だけではなく、なるべく図を見て伝わる資料をつくるよう心掛けています。
あとは結論から話すとか、とにかく伝わりやすくするということは、この会社、この環境だからこそ強く意識するようになりましたね。

K.K.
他にも、国や文化による違いを感じることは結構ありますね。例えば、中国の製造会社ってすごくフットワークが軽いですよね?

W.K.
確かに、中国の会社っていつも走っているイメージがありますね。今、中国のお客様から依頼を受けているのですが、チャンスがあったら必ずものにしようと素早く行動する印象です。
すぐに動いて、いろいろな方法にトライし、パッと修正してしまう。日本だと1、2週間かかるようなものを、「それ数日でやっちゃう?」といった感じです。
一方で、日本は「これは難しいからこの時間がほしい」と慎重です。どちらもいい点があって、そのバランスを取りながらものづくりができるのが、私はいいと思っています。
また現在、インドネシア人の私、他はミャンマー、日本、中国の方という環境で仕事をしています。インドネシア人ばかりと接していた入社前と比べて、考え方や物の見方など自分の世界が広くなったと感じます。立ち振る舞いや態度に文化の違いを感じることもあり、自分の態度や言動についても気を付けるようになりました。

K.N.
トランスナショナルということに限らないのですが、前職に比べて意見交換の場が多いと感じます。自分と異なる意見も柔軟に受け入れながら、そのうえでみんなで話し合って仕事を進めていく。そんな環境があると思います。
CHAPTER 05
もっとグローバルな環境、
できれば海外事業所で
働きたい。

最後に、今後の目標について教えてください。

K.N.
設計を始めて2年目になります。仕事で行き詰まると、上司や先輩にまだまだ「どうしたらいいですか?」って聞くことが多いです。だから、「こうしたいんですけど、どう思いますか?」と聞けるようになりたいですね。自分で筋道を立てられ、自分なりの考えや意見を持った設計者に成長できたらと思います。

K.H.
今経験している評価試験をベースに、技術的な知識をもっと深くしながら、一設計者として自分なりに考えながら設計できるようになりたいです。

Y.A.
自分のキャリアの目的はSMKのビジョンと一致しています。これからも新しい価値を創造して、社会に貢献したいです。また、SMKにはいろいろな部署があるので、人事なども経験してみたいですね。

W.K.
今後2、3年は、同じ部署で立派なエンジニアになることが目標です。その後は、もっとグローバルな環境、機会があれば海外事業所でも働いてみたいです。その時は、営業など他の職種に挑戦してみるのもいいかも(笑)。

K.K.
主任、グループリーダーとして、同じグループの人から質問や相談を受ける立場になりました。今まで経験したことを、もっとうまく伝えていけるようになりたいですね。
あとは、新しい技術もどんどん出てきて、過去の経験だけだと立ちゆかなくなるので、情報をキャッチ、勉強しつつ、自分の仕事に取り込んでいきたいと思います。
